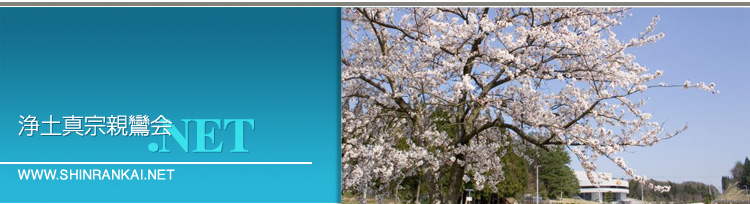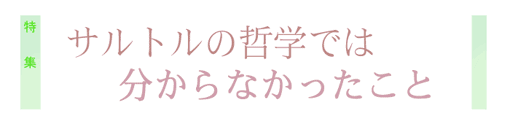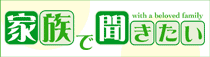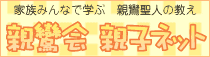カンボジアで見た現実
野崎 美幸さん(仮名)
女子大のフランス文学科3年の夏休み、カンボジアへ出掛けた。東洋の代表的な寺院遺跡、アンコールワットをこの目で見てみたかったからだ。
延々と続く田んぼと、貧しい村落をバスで抜けると、やがてアンコールワットが壮大な姿を現す。
ところが、正面の大きな門の片隅に、浮浪者達が固まっていた。皆、地雷で片足をなくしている。まだ年端の行かぬ子供もいた。口を開いたまま、あらぬ方を見つめるその目には光はなかった。内戦が続いたポル・ポト政権時代の悲しい爪痕である。
「これが世界の現実なのだ」
日本での平和な生活が、まるで夢に思えた。眼前の現実に目をつぶり、自分の幸せだけをもとめる人生でいいのか?そんな思いにさいなまれつつ、目を伏せ、その場を通り過ぎた。
存在は無意味か
日本へ帰ると、就職活動、卒業論文などの準備に取りかからねばならなかった。
友人たちは、卒論のテーマにスタンダールやジイドなど、専ら恋愛文学を選んでいた。
私は、恋愛など実生活で十分ではないか、もっと普遍的で、力のある確かなものを知りたいと思った。
選んだのは、フランスを代表する哲学者サルトル。膨大な彼の著作の中から、有名な小説『嘔吐』に的を絞った。
概要は、家族もなく、独りブービルという港町に住み、図書館で調べ物を続けるロカンタンが、ある日突然、平凡な物体をみて吐き気を覚える。繰り返されるその体験を突き詰めるうち、すべてのものは、たまたま「そこにある」にすぎず、存在することにに何の意味もない。人間も同じ、という不条理に気づき懊悩する。
小説は最後、ロカンタンが芸術・創作の世界に、唯一生きる意味を見出して終わるが、納得がいかなかった。「人間には、そんな幸福しかないのだろうか?」
人間存在の無意味さを散々突きつけられた揚げ句、結論を放り出された感じがした。何十回と読み返したが、思いは変わらなかった。
後年サルトルは、戦う知識人として政治活動に没入していく。
「ただ頭で考える青白きインテリではいけない、自ら選択し、行動し、現実に切り込め、自分自身に刻印を押せ……」。彼の哲学はそう言っているように思われた。
医学部へ転身
サルトルの思い描いた幸福とはなんだったのか?それを知るには自らも行動を起こさなければならない。山本さんは級友たちの安易な就職活動を潔しとせず、意義ある仕事を模索し続けた。
だが、意義とは何か。考え出すと、たちまち途方に暮れた。悩んだ末、思いついたのが医師だった。人命を救う。病に苦しむ人を助ける。これなら生涯掛けて悔いのない仕事、と思われた。
医学部への転身は困難だったが、1年間の猛勉強の末、医学部に合格した。
入学して間もないころ、仏教について語る同級生がいた。
「どう生きても、その先にあるのは死ではないか。なのに、なぜ生きる?」
そう問いかける級友の言葉に、虚を突かれる思いがした。死は盲点だった。医学は人命を救うといっても、本当は死を先送りするだけである。死を前に生きる意味を問われて何と答える?だがそれがわからねば、医学の延命も意味をなさぬことに気がついた。
その後、親鸞会で仏教の話を聞くようになり、まず驚いたのは、親鸞聖人の確信に満ちた断言の数々だった。
「噫、弘誓の強縁は多生にも値いがたく、
真実の浄信は億劫にも獲がたし」(教行信証)
真実を冷徹にみつめ、人間を底の底まで見極められた親鸞聖人がかくも大歓喜し、絶叫される世界がある。サルトルの示そうとした哲学上の救いとは、まるで次元を異にする幸福が仏教にあると感じた。
人生には、これ一つ果たさなければならない大事な目的がある。それは、現在、完成できる。私が知りたいと思っていたすべてが、親鸞聖人の教えにあった。
今、心から言いたい。
「弥陀の本願は、すべての人が相手だから、すべての人生に意味がある。それを知ってこそ医学にも、命が吹き込まれるのです」と。